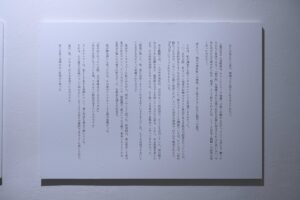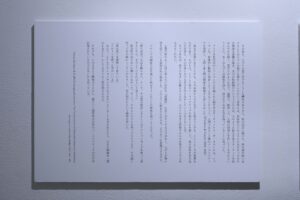『触れたら、死ぬ』
於展覧会「im/pulse 脈動する映像」2018年6月2日(土)〜7月8日(日)京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA
制作者:村津蘭

ベナン南部において点在する先祖霊仮面結社クビトのパフォーマンスにおけるクビトの布に触れたら死ぬという命題について思考した映像と布によるインスタレーション。
クビトは元々ヨルバ系の先祖霊の結社とされ、男性のみが加入できる。クビトが纏う布には、天上の世界の力が入っていて、治癒的で魔術的な力があり「クビトの布に触れたら、死ぬ」とされる。そのため、クビトが広場で踊るとき、布に触った人間は逃げまどう。しかし一方で、結社内外には「布に触っても実際は死なない」という一定の共通理解も存在している。それにも関わらず布への畏怖は存在する。こうした畏怖はどのように醸成されるだろうか。「布」というモノはその際にどのように関与するのか。それは日本における宗教的な畏怖の感覚とどのようにつながっているのか。こうしたことを問いを念頭にした、文字の書かれた布と二面に映し出された映像のインスタレーション。
『触れたら、死ぬ』『人・モノ・物神』の紙上の展示と分析については『im/pulse―脈動する映像―』(2020年 京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA)参照
『人・モノ・物神』
於展覧会「im/pulse 脈動する映像」2018年6月2日(土)〜7月8日(日)京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA
制作者:村津蘭、矢野原佑史、 ふくだぺろ
「どのようにしてモノは力を持つようになるのか」という問いをめぐる参加型インスタレーション。
人類学的な視点から「芸術的なもの」を議論したジェル[Gell 1998]は、芸術的なものを、美学的に理解するのではなく、人もモノも、それが遂行的な力を発揮するという意味で「エージェンシー」を持つ存在として扱い、その連関のプロセスから呪術や芸術がどのように作用するかから理解する視覚を示しだした。一方で、インゴルド[2017]は、エージェンシーを設定する態度は、モノの対象性に焦点をあてるが余りに、生の世界を死んだようなモノとして捉えているのだと批判し、生の世界の中で生じる相互応答と、そこで描かれる軌跡への注目を促す。それでは、モノが力を持つようになるとき、そこにおける軌跡はどのようなものだろうか。
本展示である布小屋は、「身を守るためのモノを作らなければならない」という命題を観覧者に提示し、実際にモノを作ってもらい祭壇に捧げるという行為を要請する。そのプロセスを通して、参加者には「モノが力を持つ」実際の軌跡を経験してもらうことを狙った。また、インスタレーション自体が、それがどのような経験であるのかを参加者や作られたモノとの対話から分析するという製作者の「フィールド」としての役割を担ったのも、この展示の特色である。
於新宿眼科画廊、2025年2月14日~2025年2月19日
制作者:村津蘭、河本梨奈、藤本哲明
この展示は、文化人類学・映像人類学者と、写真家、詩人との協業によって行う実験的なものである。表現媒体や志向が異なる三人が対話を重ね、一つの展示を作ることにより、それぞれの分野の拡張性とその可能性を探究した。また、展示をめぐって異なる分野の表現者とトークをすることにより学問の表現としての展示の意味を考えた。